こんにちは。
「宇宙ってどこから宇宙なんだろう…」「宇宙の果てには一体何があるんだろう…」
今回は、そんな疑問を持つ方に向けて、地表から宇宙までの距離や大気圏の距離、宇宙の果てや外側についてなどをそれぞれ分かりやすく解説していきます。
- 地表から宇宙までの距離を知りたい
- どこから宇宙なのか知りたい
- 大気圏の距離を知りたい
- 宇宙の果てについて知りたい
- 宇宙の外側には何があるのか知りたい
- 宇宙の外側に出ることはできるのか知りたい
地面から宇宙までの距離はどれくらい?

地表から高度100km以上が一般的に宇宙とされており、これは国際航空連盟(FAI)が定めた「カーマンライン」に基づいています。
一方、米国空軍は高度80kmからを宇宙としています。
大気はこの高度になると極めて薄くなり、宇宙空間とみなされます。国際宇宙ステーション(ISS)はさらに上空の約400kmを周回しています。
このラインを越えると空気がほとんどなくなり、地球の重力圏内ではあるものの「宇宙空間」とみなされます。
たとえば、国際宇宙ステーション(ISS)は地上から約400kmの軌道を周回しており、それでもまだ「低軌道」に属します。
私たちの暮らす地表から見れば、宇宙は意外と近くにあるのです。
大気圏の距離と構造は?

地球の大気は数層に分かれており、それぞれの高度によって呼び方や特徴が異なります。
- 対流圏(地上〜約12km):私たちが暮らす層で、天気現象が起こる。
- 成層圏(12〜50km):オゾン層が存在し、気流は安定している。
- 中間圏(50〜80km):気温が急激に低下する寒冷な層。
- 熱圏(80〜500km):オーロラが見られ、ISSがこの中を周回。
- 外気圏(500km〜約10,000km):大気が極めて薄く、ほぼ宇宙空間。
大気圏は地球を取り巻く空気の層で、一般には地表から約100kmまでとされていますが、定義には幅があります。
大気圏は高度に応じて「対流圏」「成層圏」「中間圏」「熱圏」「外気圏」の5層に分かれ、それぞれ異なる特徴を持っています。
宇宙との境界は明確ではなく、FAIは100km、米国空軍は80kmを宇宙の始まりと定義しています。
大気は高度が上がるにつれて薄くなり、徐々に宇宙空間へと移行します。
そのため、人工衛星が飛ぶ高度でも大気の影響が残ることがあります。
つまり、大気圏の“端”は明確に定まっているわけではありませんが、おおむね1000km付近までが「地球の大気圏」と考えられています。
高度1000kmは宇宙?それとも地球圏内?
高度1000kmは、確かに「宇宙空間」とされますが、地球の重力圏や磁気圏の影響下にある領域でもあります。
高度1000kmは大気圏の最上層「外気圏」にあたり、人工衛星やISSが飛行する領域です。
この高度では、大気は非常に薄く人工衛星や通信衛星が多数存在します。
たとえば、気象衛星「ひまわり」などの静止衛星はもっと高く、約3万6000kmの位置にあります。
大気はほとんどありませんが、希薄なガスとプラズマが混在し、複雑な現象を引き起こします。また、この高度には宇宙ゴミも多く存在します。
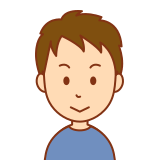
つまり、1000kmは宇宙空間ではあるものの、まだまだ「地球に近い宇宙」といえるでしょう。
宇宙の果ての画像は存在する?
現在、私たちが観測可能な「宇宙の果て」の画像は、宇宙マイクロ波背景放射(CMB)として記録されています。
これはビッグバンから約38万年後の宇宙の姿で、プランク衛星やWMAPによって撮影されました。
画像には温度のムラ(揺らぎ)が描かれており、現在の銀河や構造の“種”となるものです。
ただしこれは「可視宇宙」の果てであり、宇宙全体の果てではないことに注意が必要です。
こちらのページから「ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡」が撮影したこれまでで最も遠い宇宙の画像を見ることができますよ↓

宇宙の果てを描いた「宇宙図」とは?
「宇宙図」は、宇宙の構造や進化を図解したもので、NASAや科学研究機関によって公開されています。
特に有名なのが「可視宇宙の構造」を示したログスケール宇宙地図。
この図では、地球を中心にビッグバンの背景放射までの広がりを視覚的に理解できます。
銀河団、銀河、クエーサー、背景放射の順で並び、宇宙のスケール感を直感的に掴める貴重な資料です。
円形の中に宇宙空間を閉じ込めた宇宙地図についてはこちらのページでも詳しく紹介されています↓

宇宙の外には何がある?

宇宙の外側には一体何があるのか、これは科学でも哲学でも難題です。
宇宙の外に何があるかはまだ解明されていません。
観測可能な宇宙は約465億光年までですが、その外側は観測できず、
- 宇宙が無限に広がっている
- 別の宇宙がある
- 宇宙が特殊な形をしていて外側にいけない
といったさまざまな仮説があります。
しかし、約465億光年より先は光が届かず観測ができないため、これらの仮説は確証を持って語ることができません。
今後の観測技術や理論物理学の進展により、宇宙の果てに何があるのかが少しずつ明らかになると期待されています。
今後の研究がその謎を解く鍵になると期待されています。
宇宙が特殊な形をしているという説は、宇宙が3次元的に「曲がった」空間で、風船の表面のように、有限ではあるが「外」はないという構造だという説です。
また、宇宙には「外」は存在しないという可能性もあり、「宇宙の外に何があるか?」という問いは、現代物理学の枠組みでは意味をなさないこともあります。
ただし、多元宇宙論やブレーン宇宙論などでは、「外」に別の宇宙が存在するという仮説も提案されています。
宇宙の外側とは何か?宇宙の外側までの距離は?
「宇宙の外側」とは、あくまで観測可能な宇宙の外という意味で使われることが多い言葉です。
現在の技術では約465億光年先までが観測可能とされていますが、その向こう側にも宇宙空間や物質が存在している可能性は高いと考えられています。
しかし、光がまだ私たちに届いていないため、観測できず理論的な推測にとどまります。
つまり、宇宙の外側は「未観測領域」であり、謎に包まれているのです。
宇宙の外に出ることは可能か?
現時点では、「宇宙の外に出る」ことは不可能です。
なぜなら、この宇宙に存在する全ての物質は光の速度を超えることができないため、それ以上の速度で広がっている宇宙の外側には到達することはできないからです。
アインシュタインの相対性理論によると、光の速さは普遍的な限界であり、いかなる質量を持つ物体も光速を超えることはできないとされています。
また、私たちが存在するこの宇宙自体が、時空そのものを包んでおり、その“外”は定義できないからです。
もしも多元宇宙が存在するなら、ワープ航行などの理論的には別の宇宙にアクセスする技術が将来開発される可能性もありますが、現代の物理学と宇宙工学の範囲では、宇宙の外に出るという発想はSFの域を出ません。
とはいえ、そうした問いが未来の科学の扉を開くかもしれません。
まとめ
今回は、地表から宇宙までの距離や大気圏の距離、宇宙の果てや外側についてなどを解説してきました。
実はしっかりと宇宙との境界線は決められているのですね。
高度100㎞から宇宙と聞くと意外と近いなと思ってしまいますが、まだまだ宇宙は謎だらけなので、これからの新発見に期待ですね!
最後まで読んでいただきありがとうございました。

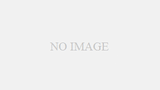
コメント